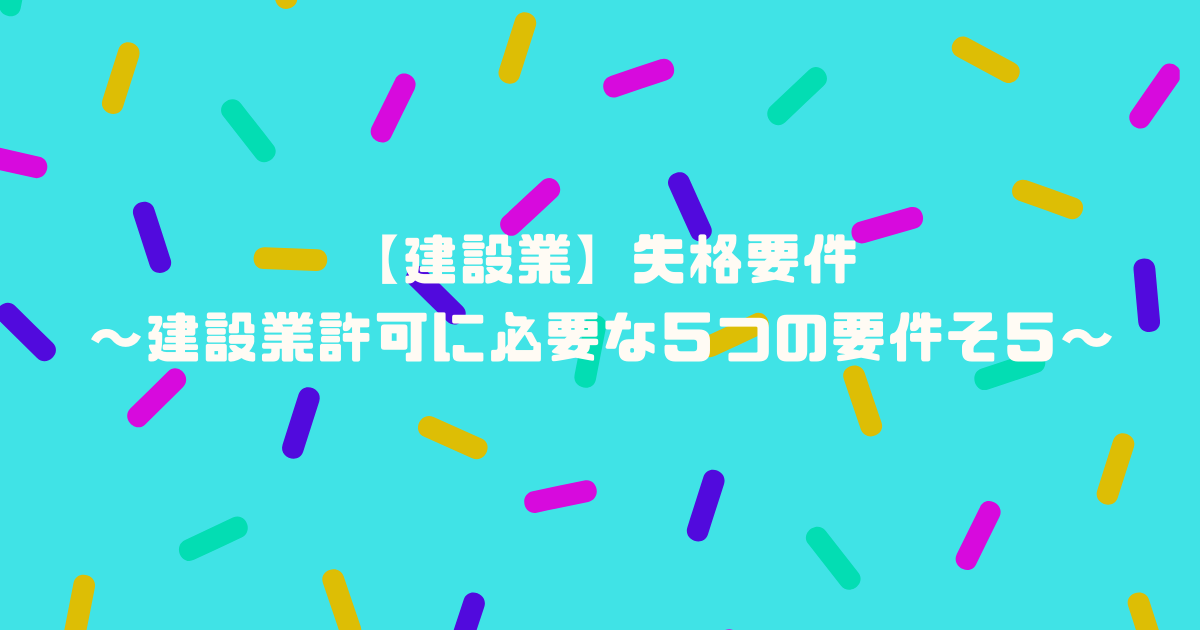妊娠すると、楽しみな気持ちが大きくなる一方、健診や検査といった医療費の負担が大きくなり、不安を感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では、妊娠と出産で自治体や健康保険などから受けられるお金の支援について、みんながもらえるお金をご紹介します。

助成金・給付金 早わかり表
○=もらえる、×=該当しない、△=条件による
| 妊婦健診費の助成 | 出産育児一時金 | 乳幼児の医療費助成 | 児童手当 | 医療費控除 (確定申告) | 高額医療費 | 出産手当金 | 育児休業給付金 | 病手当金 | 退職者の所得税還付申告(確定申告) | |
| 主婦 ・ 扶養 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 社保 ・ 働く |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 国保 ・ 働く |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
| 社保 ・ 退職 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
| 国保 ・ 退職 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ |
主婦・扶養:専業主婦、配偶者の扶養内の方
社保・働く:社会保険に加入していて、産後も仕事を続ける方
国保・働く:国民健康保険に加入していて、産後も仕事を続ける方
社保・退職:社会保険に加入していて妊娠中に仕事を辞める(辞めた)方
国保・退職:国民健康保険に加入していて妊娠中に仕事を辞める(辞めた)方
妊婦検診費の助成
妊娠中に受ける妊婦健診にかかる費用を補助する制度です。
妊婦健診は医療費が全額自己負担のため、高額になります。この負担を減らすため、費用を助成してくれます。
制度について
| もらえる人 | 主婦・扶養、社保・働く、国保・働く、社保・退職、国保・退職 |
|---|---|
| 対象者 | 妊娠が確定した人 |
| 助成される金額 | 妊婦健診14回分程度の費用 |
| 手続きに必要なもの | 妊娠届、身分証明証 |
| 申請時期 | 妊娠確定後、医師や助産師の指示がでたら |
| 受け取り時期 | 妊娠届を提出したその日 |
| 申請・問い合わせ先 | 住んでいる市区町村の役所(または保健所)の担当窓口 |
手続きの流れ
- 妊娠が確定したら役所(又は保健所)に妊娠届を提出し、母子健康手帳と一緒に受診助成券をもらう
※妊娠届の用紙は受診した医療機関でもらう事が多く、氏名、住所などの必要事項を記入し役所へ提出します。
※地域によっては役所ではなく保健所で手続きする場合があります。 - 妊婦健診前
受診助成券の本人記入欄に必要事項を記入し、医療機関へ持参
※自治体により本人記入欄が無い場合があります。 - 妊婦健診時
受診助成券を提出し会計時に助成額を差し引いた金額が請求されるので支払う
ポイント・注意点
- 助成回数や助成金額は自治体によって異なりますが、おおむね14回分となっているケースが一般的です。また、現金ではなく紙の券で支給されることがほとんどです。
- 里帰りをする場合
里帰り出産に伴い、お住まいの自治体以外の医療機関で受診される場合は、自治体が異なるため受診助成券が使用できません。この場合、後から払い戻しができる償還払い制度があるので、里帰り中に健診にかかった費用を出産後にお住まいの役所窓口へ提出することで、お金が戻ってきます。健診の領収証は必ず保管する必要があります。 - 妊娠中に別の市町村へ引越しをする場合
引越し先の医療機関では、元の自治体が発行した受診助成券が使用できません。元の自治体が発行した未使用の受診券を転居先の役所へ提出することで、転居先で使用できる受診助成券を発行してもらえます。引越しが決まっていても未使用の受診券は捨てず、引越し先の役所へ必ず持って行きましょう。 - 受診助成券を紛失した場合
受診助成券は原則として再発行していないようです。紛失しないよう十分お気をつけください。
出産育児一時金
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合、入院・分娩費として健康保険から基本42万円がもらえます。多胎児を出産された場合は、その人数分支給されます。
申請方法は「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請方式」の3種類あり、直接支払制度を利用する場合がほとんどです。直接支払制度を導入していない小規模の産院などは、受取代理制度が利用できるケースもあります。直接支払制度を利用できるかどうかはかかりつけの医療機関に確認してみましょう。
制度について
| もらえる人 | 主婦・扶養、社保・働く、国保・働く、社保・退職、国保・退職 |
|---|---|
| 対象者 | 健康保険の加入者またはその被扶養者で、 妊娠4ヶ月以上で出産あるいは流産した方 |
| もらえる金額 | 基本42万円(子ども一人につき) |
| 手続きに必要なもの | 直接支払制度 :意思確認書など 受理代理制度 :出産育児一時金等支給申請書(受理代理用)、申請者の振込先の口座番号、申請者の健康保険証、印鑑 産後申請方式 :出産育児一時金申請書、直接支払制度を利用していないことの証明書(提出を求められた場合)、入院・分娩費の領収証、身分証明書 |
| 申請時期 | 直接支払制度、受理代理制度:妊娠中 産後申請方式:産後 |
| 受け取り時期 | 直接支払制度、受理代理制度:退院の精算時 産後申請方式:産後 |
| 申請・問い合わせ先 | 直接支払制度:産院 受理代理制度、産後申請方式:自分が加入している健康保健の窓口 (国保の人は役所の窓口担当) |
手続きの流れ
ここでは直接支払制度について説明します。
- 妊娠中
医療機関で意思確認書をもらい、記入後、医療機関へ提出 - 退院時
入院・分娩費が42万円を超えた場合、差額分を支払う - 産後
入院・分娩費が42万円を下回った場合、健康保険に差額の申請をする - 申請後
申請した差額が健康保険より振り込まれる
ポイント・注意点
- 産後申請方式
申請期間は、出産した翌日から2年間です。2年を1日でも過ぎると給付が受けられなくなるのでご注意ください。 - 資格喪失後(退職後)の出産育児一時金
勤め先の健康保険に1年以上加入しているママが、資格喪失から6ヶ月以内に出産した時は、ママの退職前の健康保険に申請することも可能です。
乳幼児の医療費助成
赤ちゃんの医療費を自治体が全額、または一部助成する制度です。病院にかかった時に医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料〜減額になります。
制度について
| もらえる人 | 主婦・扶養、社保・働く、国保・働く、社保・退職、国保・退職 |
|---|---|
| 対象者 | 健康保険に加入している子ども (自治体により対象年齢は異なります。) |
| 助成される金額 | 医療費の全額、または一部(自治体によって異なります。) |
| 手続きに必要なもの | 子どもの健康保険証、印鑑、申請者と配偶者の身分証明書 |
| 申請時期 | 出産後、なるべく早く |
| 受け取り時期 | 申請時にその場で交付、または後日郵送で届く |
| 申請・問い合わせ先 | 住んでいる市区町村の役所の担当窓口 |
手続きの流れ
- 妊娠中
住んでいる自治体の助成内容や手続き方法をチェック - 出産後
役所へ出生届を提出し、会社へ赤ちゃんの健康保険の加入を依頼する - 保険証を受け取り後
赤ちゃんの健康保険証を持って役所で助成の手続きを行う
※自治体により電子申請が可能な場合があります。 - 申請後
乳幼児医療証が届く - 病院受診時
乳幼児医療証を提示すると医療費を助成してもらえる
ポイント・注意点
- 手続き前に医療機関にかかった場合
一度、医療機関の窓口で医療費を支払う必要がありますが、自治体によっては、後日払い戻しの手続きをすると助成が受けらる場合があります。領収証は必ず保管しておきましょう。 - 住んでいる地域以外での受診した場合
乳幼児医療証を利用できない場合があります。後日、住んでいる自治体に申請すれば、医療費の払い戻しが可能な場合があるので、領収証は必ず保管しておきましょう。
児童手当
0歳〜中学校卒業までの児童を養育している家庭に育児にかかる費用が支給される制度です。
制度について
| もらえる人 | 主婦・扶養、社保・働く、国保・働く、社保・退職、国保・退職 |
|---|---|
| 対象者 | 中学校卒業までの子どもを持つ世帯主 (共働きの場合は収入が多い方) |
| もらえるお金 | 3歳未満:月1万5千円 3歳〜小学校卒業まで:月1万円 中学生:月1万円 |
| 手続きに必要なもの | 申請者の振込先の口座番号、申請者の健康保険証、母子健康手帳(必要な場合)、印鑑、児童手当認定請求書、児童手当用所得証明書または課税証明書など(妊娠中に別の自治体に引越しした時などに必要) |
| 申請時期 | 出産後、なるべく早く |
| 受け取り時期 | 年3回 2・6・10月の10日前後 |
| 申請・問い合わせ先 | 住んでいる市区町村の役所の担当窓口 |
手続きの流れ
- 妊娠中
手続きに必要なものを役所に確認
※ホームページなどに掲載されています。 - 出産後
役所に出生届を提出
出生届を提出した後、そのまま役所で手続きを行う - 申請後
2・6・10月の年3回に分けて、4ヶ月分(前月までの分)ずつまとめて振り込まれる
ポイント・注意点
- 申請時期について
手続きをした翌月分から支給されます。申請が遅れるとその分遡ってもらうことはできないので、ご注意ください。 - 15日特例
月末に出産した場合、誕生の翌日から15日以内に申請して認定されれば、誕生月に手続きしたとみなされます。出生届を提出した後すぐに手続きをすると安心です。 - 所得制限について
2022年10月以降は扶養者のいずれかが年収1200万円以上の場合、支給停止になります。詳しくは自治体のホームページなどで確認をしてください。
医療費控除(確定申告)
1年間(1月〜12月)で家族全員の医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくる制度です。妊娠・出産で医療費がかさむので、ぜひ申告しましょう。共働きの場合は、収入の高い方が医療費控除を申請した方が戻ってくる金額が大きくなりやすいです。
制度について
| もらえる人 | 主婦・扶養、社保・働く、国保・働く、社保・退職、国保・退職 |
|---|---|
| 対象者 | 家族全員の医療費の合計が1年で10万円を超えた人 または 所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%を超えた人 |
| 戻るお金 | 源泉徴収で前払いした所得税−実際の所得税 |
| 手続きに必要なもの | 確定申告書、医療費や交通費の明細書、支払調書(申告者が自営業の場合など)、保険金などで補填される金額がわかるもの(明細書に記載すれば不要)、医師の証明が必要な場合は証明書、申告書の振込先の口座番号、申告者のマイナンバーがわかるもの、源泉徴収票(申告者が会社員・公務員の場合など) |
| 申請時期 | 退職した翌年1月から5年以内 |
| 受け取り時期 | 申告してから約1〜2ヶ月後 |
| 申請・問い合わせ先 | 住んでいる地域の税務署 |
手続きの流れ
- 1〜12月
1月1日から12月31日までの家族全員の医療費の領収証を集めておく - 翌年1月頃
1月1日から12月31日までの家族全員の医療費を合計する
確定申告書を入手する
(国税庁のホームページからダウンロード可能、e-taxで電子申請も可能)
確定申告書に必要事項を記入して計算し、税務署に提出する - 申告から1〜2ヶ月後
申告者名義の口座に還付金が振り込まれる
ポイント・注意点
- 受け取った給付金について
出産育児一時金、高額医療費や生命保険などの受け取った給付金は医療費から差し引いて計算をします。不備があると税務署から是正を求められるので、ご注意ください。 - 領収証
医療費の領収証は5年間の保管義務があるので、なくさないよう管理しておきましょう。 - 交通費
通院に必要な交通費(公共交通機関を利用したもの)も明細に書き込んでおきましょう。 - 医療費として認められるもの・認められないもの
認められるもの ・妊婦健診費
・入院費、分娩費
・診療費、治療費
・治療に必要な薬代
・歯の治療費
・赤ちゃんの健診費、入院費
・医師が必要と認めた松葉杖や補聴器などの購入費
・治療のためのはり・きゅう・マッサージ代
・異常が発見された場合の人間ドックの費用
・出産時のタクシー代や、その際の駐車場代
・通院にかかった交通費(公共交通機関を利用したもの)
・赤ちゃんの通院のための交通費(公共交通機関を利用したもの)
など認められないもの ・妊娠検査薬代
・出生前検査費
・マイカーで通院する時のガソリン代や駐車場代
・緊急でない通院で利用したタクシー代
・里帰り出産のための帰省費用
・異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
・病気予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク剤
・医師の処方以外の漢方薬代
・見た目を良くするための歯の矯正費
・メガネ、コンタクトレンズ代
など
高額医療費
1ヶ月間のうち同じ医療機関で支払った医療費が一定金額(所得に応じた自己負担限度額)を超えた場合に払い戻しが受けられる制度です。切迫流産、切迫早産や帝王切開などは、医療費に健康保険が適用されるため、利用することができます。
制度について
| もらえる人 | 主婦・扶養、社保・働く、国保・働く、社保・退職、国保・退職 |
|---|---|
| 対象者 | 健康保険が適用される治療をした人で、1ヶ月の自己負担限度額を超えた人 |
| 助成される金額 | 自己負担限度額を超えた金額分 |
| 手続きに必要なもの | 事前認定の場合:健康保険限度額適用認定証、健康保険証 事後申請の場合:高額医療費支給申請書、健康保険証、医療機関の領収証 |
| 申請時期 | 事前認定の場合:入院予定日、またはその前 事後申請の場合:退院後 |
| 受け取り時期 | 事前認定の場合:退院後時に自己負担限度額を支払う 事後申請の場合:申請から約1〜3ヶ月後 |
| 申請・問い合わせ先 | 健康保険の管轄先 国保の場合は市区町村の窓口 |
手続きの流れ
事前認定
- 入院前、または入院時
入院予定期間を医師に確認の上、限度額認定の申請書をもらい提出する
または
入院予定日、またはその前に健康保険の窓口か会社の総務課(国保の場合は役所)で申請書をもらい記入後、提出する
(申請用紙は健康保険のホームページなどから入手することも可能です。) - 1〜2週間後
加入している健康保険(国保の場合は役所)から健康保険限度額認定証が発行される - 入院時、または入院中
入院時に健康保険限度額認定証を提示する。退院時に自己負担限度額のほか、食事代や差額ベッド代などを支払う
健康保険限度額適用認定証の手続については、下記記事で詳しく解説をしているので、ぜひご参照ください。
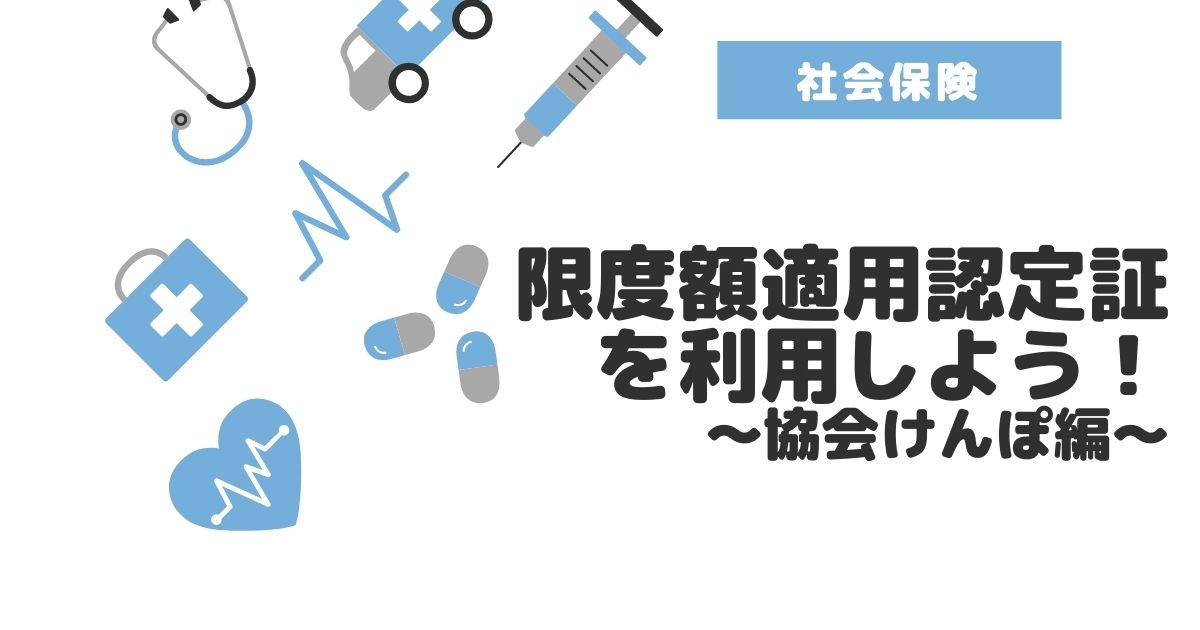
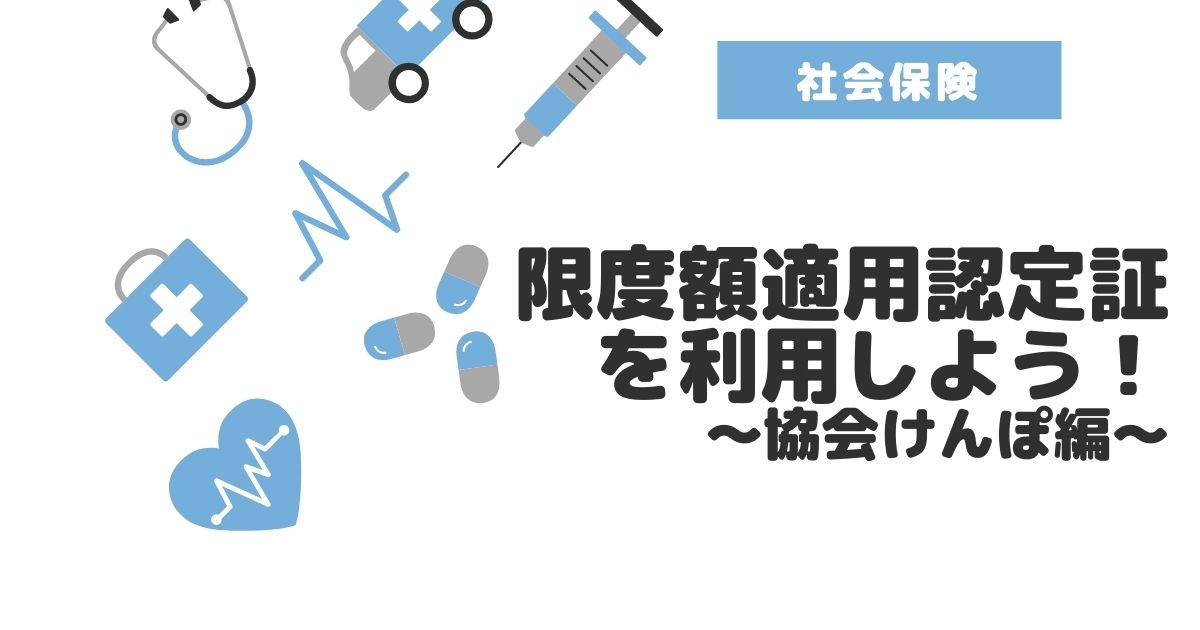
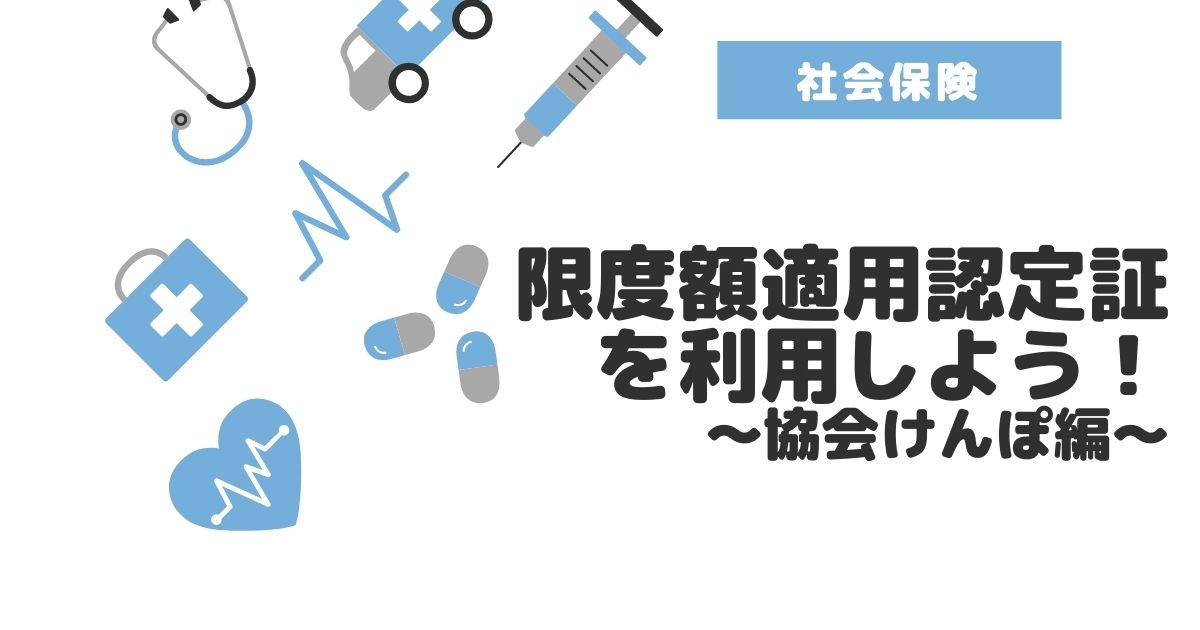
事後申請
- 退院時
医療費を窓口で支払い、領収証をもらっておく - 退院後
加入している健康保険(国保の場合は役所)で申請書をもらい、高額医療費の支給を申請する
(申請用紙は健康保険のホームページなどから入手することも可能です。) - 申請後
約1〜3か月後に自己負担限度額を超えた分が振り込まれる
ポイント・注意点
- 入院が月をまたぐ場合
医療費は月末で精算されるため、自己負担限度額を超えないことがあるのでご注意ください。
まとめ
自治体などが様々な制度を用意していますが、待っているだけではもらえません。安心して赤ちゃんを迎えられるよう、必ず自分で調べてこれらの制度を活用しましょう。