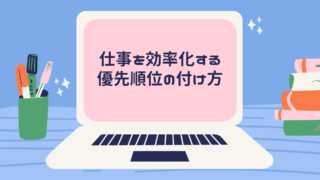妊娠すると、楽しみな気持ちが大きくなる一方、検診や検査といった医療費の負担が大きくなり、不安を感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では、妊娠と出産で自治体や健康保健などから受けられるお金の支援について、要件に該当する方がもらえるお金をご紹介します。

助成金・給付金 早わかり表
○=もらえる、×=該当しない、△=条件による
| 妊婦健診費の助成 | 出産育児一時金 | 乳幼児の医療費助成 | 児童手当 | 医療費控除 (確定申告) | 高額医療費 | 出産手当金 | 育児休業給付金 | 病手当金 | 退職者の所得税還付申告(確定申告) | |
| 主婦 ・ 扶養 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 社保 ・ 働く |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 国保 ・ 働く |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | × |
| 社保 ・ 退職 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
| 国保 ・ 退職 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ |
主婦・扶養:専業主婦、配偶者の扶養内の方
社保・働く:社会保険に加入していて、産後も仕事を続ける方
国保・働く:国民健康保険に加入していて、産後も仕事を続ける方
社保・退職:社会保険に加入していて妊娠中に仕事を辞める(辞めた)方
国保・退職:国民健康保険に加入していて妊娠中に仕事を辞める(辞めた)方
出産手当金
加入している健康保険から産前産後の働けない期間の生活を支えるために給付金が支給される制度です。加入している健康保険によっては支給されない場合があるので、勤め先に受給資格の確認しましょう。
制度について
| もらえる人 | 社保・働く 社保・退職(退職時期などの条件を満たせばもらえる場合あり) |
|---|---|
| 対象者 | 勤め先の健康保険に加入していて産後も仕事を続ける人 |
| 助成される金額 | 日給の3分の2×産休の日数分 |
| 手続きに必要なもの | 健康保険出産手当金支給申請書、申請者の振込先の口座番号、印鑑、健康保険証 |
| 申請時期 | 産後56日経過後(産休終了後) ※産休の途中でも提出することが可能な場合もあります。 |
| 受け取り時期 | 申請から約2週間〜2ヶ月後 |
| 申請・問い合わせ先 | 勤め先の健康保険担当窓口または各健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の窓口 |
手続きの流れ
- 妊娠中
勤め先で受給資格を確認する - 産休前
勤め先などで健康保険出産手当金支給申請書をもらい、必要事項を記入する - 入院時
健康保険出産手当金支給申請書を持っていき、医療機関で申請書にある出産の証明欄への記入を依頼する - 産休終了後
申請書を勤め先へ送り、必要事項の記入と、健康保険への提出を依頼する
※自分で健康保険へ提出する場合もあるので、勤め先に確認をしてください。 - 申請後
約2週間〜2ヶ月後に指定の口座にお金が振り込まれる。
ポイント・注意点
- 会社から給料が出る場合
産休中に会社から給料の3分の2以上が出る場合、出産手当金はもらえません。給料の3分の2未満が支給される場合は、給料の3分の2との差額分が健康保険から支給されます。産休中の給料支給については、勤め先に確認しておきましょう。 - 契約社員の場合
勤め先の健康保険に加入し、産休を取得できれば問題ありません。ただし、派遣会社を通した契約の場合は、条件を満たしているかどうか派遣元の会社に確認しましょう。 - 退職した場合
退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があるなど、条件を満たしている場合は出産手当金を受け取れる可能性があります。一度、勤め先の健康保険担当窓口または各健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の窓口へご確認ください。
育児休業給付金
加入している雇用保険から育児休業中に生活を支えるために給付金が支給される制度です。産休が終了した翌日から子どもの1歳の誕生日までが対象期間で、もし保育園に入園できなかった場合は最長2歳になるまで延長できます。
制度について
| もらえる人 | 社保・働く 国保・働く(雇用保険に加入していて条件を満たせばもらえる場合あり) |
|---|---|
| 対象者 | 雇用保険に加入していて育児休業を取得し、職場復帰をする人 |
| もらえる金額 | 育休の最初の180日:日給×0.67×育休として休んだ期間 181日目以降:日給×0.5×育休として休んだ期間 |
| 手続きに必要なもの | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、出勤簿、賃金台帳、母子手帳のコピー(出生の記録が記されているページ)、申請者のマイナンバーがわかるものなど |
| 申請時期 | 産後、育休に入る前(勤め先に申請する場合) |
| 受け取り時期 | 育休開始から約2〜5ヶ月後(初回。その後は約2ヶ月ごと) |
| 申請・問い合わせ先 | 勤め先、または勤め先を管轄するハローワーク |
手続きの流れ
- 妊娠したら
勤め先に育休が取れるか相談し、給付金がもらえるか確認する。 - 産休に入る前
育児休業給付金申請の必要書類をもらう - 産後
書類に必要事項を記入する - 育休に入る前
必要書類を勤め先に提出
※自分でハローワークへ提出する場合もあります。
勤め先の担当窓口へ確認をしてください。 - 育休中
育休開始から約2〜5ヶ月後、初回振込がされる - 育休中
約2ヶ月ごとに手続きをする。
※勤め先によっては、書類作成から提出まで一括で行ってくれる場合があります。
勤め先の担当者に必ず確認をしてください。
ポイント・注意点
- 支給要件
雇用保険に加入しており、下記の要件を満たせばもらえます。
・雇用保険に加入しており育休取得後も働き続ける人
・育休中、休業開始日前の給料に比べ、8割以上の給料が出ない人
・育休と取得し、育休開始から1ヶ月ごとの区切りに休業日が20日以上ある人
・育休開始日を起算点とし、その前2年間に、原則1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人 - 勤め先の担当者と意思疎通を!
担当者とは産休に入る前から連絡を取り合い、手続きのスケジュールを確かめておくと安心です。手続きが遅れると、給付金の振り込みが遅くなり、その間のお金のやりくりについて考えておく必要があります。
傷病手当金
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度です。
妊娠悪阻や切迫流産、切迫早産なども対象となり、連続して3日を超えて休むと4日目から傷病手当金が支給されるので、病気で4日以上休んだ場合に活用することをおすすめします。
制度について
| もらえる人 | 社保・働く 社保・退職(退職の時期によりもらえる場合あり) |
|---|---|
| 対象者 | 勤め先の健康保険に加入している人 |
| もらえるお金 | 日給の3分の2×待機期間後の休んだ日数 (日給=月給÷30) (待機期間=連続して休んだ場合の最初の3日間) |
| 手続きに必要なもの | 健康保険傷病手当金支給申請書、出勤簿(健康保険や共済組合によって不要な場合あり)、賃金台帳(健康保険や共済組合によって不要な場合あり)、申告者の振込先の口座番号、印鑑(健康保険や共済組合によって不要な場合あり) |
| 申請時期 | 2年以内 |
| 受け取り時期 | 申請から約2週間〜2ヶ月後 |
| 申請・問い合わせ先 | 勤め先の担当窓口、または各健康保険組合、勤め先を管轄する協会けんぽ、共済組合の窓口 |
手続きの流れ
- 療養中
勤め先などで健康保険出産手当金支給申請書をもらい、必要事項を記入する - 通院中
健康保険出産手当金支給申請書を持っていき、医療機関で申請書にある出産の証明欄への記入を依頼する - 申請
1ヶ月以内の復帰が見込めるなら、復帰後に勤め先へ申請書の必要事項の記入と、健康保険への提出を依頼する
復帰が1ヶ月以上になるときは、給与の締日ごと、または2〜3ヶ月分をまとめて勤め先へ必要事項の記入と、健康保険への提出を依頼する
※自分で健康保険へ提出する場合もあるので、勤め先に確認をしてください。 - 申請後
約2週間〜2ヶ月後に指定の口座にお金が振り込まれる。
ポイント・注意点
- 待機3日間の考え方
会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に出勤した場合には成立しません。
退職時の所得税還付申告(確定申告)
払い過ぎた税金を還付してもらう制度です。
年度途中で退職すると年末調整が受けられないので、自分で確定申告をする必要があります。住民税は、前年度の所得に対して課税されるので、確定申告をして課税所得が下がれば、翌年度に支払う住民税が少なる可能性があります。
ただし、退職した翌年から5年の間であればいつでも行える申請なので、余裕が無い場合は、無理せず落ち着いたタイミングで行ってください。
制度について
| もらえる人 | 社保・退職 国保・退職(条件を満たせばもらえる場合あり) |
|---|---|
| 対象者 | 仕事を辞めて再就職していない かつ退職前の給料から所得税が引かれていた人 |
| 戻るお金 | 源泉徴収票で前払いした所得税−実際の所得税 |
| 手続きに必要なもの | 確定申告書、社会保険料の明細(退職後、自分で支払った場合)、申告者の振込先の口座番号、生命保険やふるさと納税などの控除関係書類、申告者のマイナンバーがわかるもの、源泉徴収票 |
| 申請時期 | 退職の翌年1月〜5年以内 |
| 受け取り時期 | 申告してから約1〜2ヶ月後 |
| 申請・問い合わせ先 | 住んでいる地域の税務署 |
手続きの流れ
- 1月〜12月
退職時にもらう源泉徴収票を保管する - 秋頃
1年分の保険の控除証明書が送られてきたら保管する - 退職翌年の1月頃
確定申告書を入手し、必要事項を記入し、書類を税務署に提出する
(国税庁のホームページからダウンロード可能、e-taxで電子申告も可能。) - 申告から約1ヶ月〜2ヶ月後
還付金が振り込まれる。
ポイント・注意点
- 住民税
仕事を辞めても住民税は、前年の所得に対して課税されます。退職した翌年の1年間は住民税を支払う必要があるので、住民税分のお金を準備しておく必要があります。
まとめ
自治体などが様々な制度を用意していますが、待っているだけではもらえません。安心して赤ちゃんを迎えられるよう、必ず自分で調べてこれらの制度を活用しましょう。